「妊婦のための支援給付金」は、
流産や死産・中絶でも受け取れる制度です!!

2025年4月から全国で始まった新しい国の制度「妊婦のための支援給付」。
この給付金は、妊婦一人ひとりの心身・経済的負担を軽減するために設けられたもので、流産・死産・中絶を経験した方も、妊婦として一定の条件を満たせば対象となる仕組みです。
妊婦のための支援給付とは?
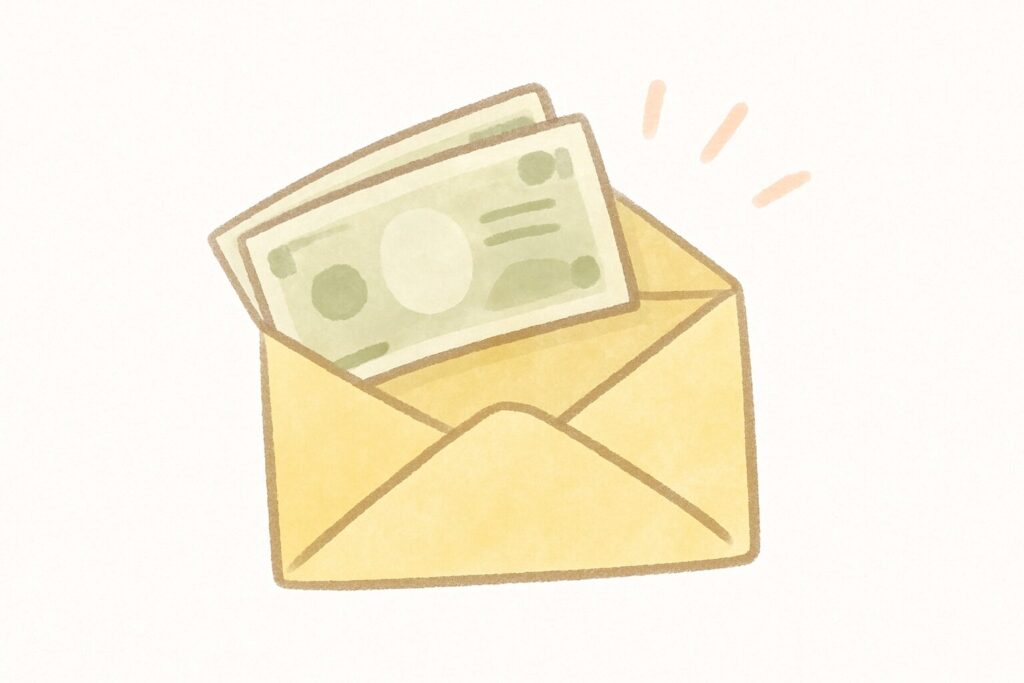
妊婦のための支援給付とは、2025年(令和7年)4月1日から施行された制度で、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児の保健および福祉の向上を目的としています。
国の子ども・子育て支援法の改正によって創設され、こども家庭庁が主導しつつ各地方自治体が運営します。
妊婦と胎児の健康と福祉を守り、負担を軽減することが目的
この制度は、妊娠期における身体的・精神的・経済的な負担を軽減し、妊婦本人とその胎児の健康および福祉を守ることを目的としています。
具体的には、産前産後の支援を通じて、安心して出産・子育てができる環境を整えることにより、母子の健やかな暮らしを支えることを意図しています。
支給は2回、合計10万円が受け取れる
支給内容は主に2回に分けられます。
【1回目】
医師に胎児心拍を確認してもらった妊娠確定後に5万円が支給されます。
【2回目】
妊娠32週以降におなかの赤ちゃんの人数につき5万円ずつが支給されます。
例えば単胎妊娠であれば5万円、双子なら10万円が支給されます。
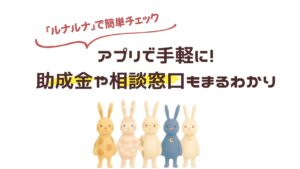
流産や死産、人工妊娠中絶の場合も給付対象

妊婦支援給付金は、妊娠届が出されていることや医療機関で「胎児心拍が確認されている妊娠」を条件に、流産・死産・人工妊娠中絶の場合でも給付対象としています。
従来の制度では出産が確定し赤ちゃんが生まれた場合のみ給付対象としていたのに対し、妊娠の過程での心身の負担や悲しみを抱える妊婦にも配慮し、支援の手を差し伸べるための改正です。
妊娠初期の胎児心拍の確認は医学的にも重要な指標であり、給付の基準として設けられています。
対象者
日本国内に住所を有し、2025年(令和7年)4月1日以降に妊婦である方(あった方)
※本制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
支給額
1.妊婦認定時に5万円
2.妊娠していたこどもの人数×5万円
申請時期と受給期限
1.妊婦であることの認定申請
産科医療機関で妊娠の事実を確認した日以降
※産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日から2年後の前日まで
2.妊娠しているこどもの数の届出
産科医療機関において、流産・死産等の事実が確認された日以降
※産科医療機関において、流産・死産等の事実が確認された日から2年後の前日まで
申請先
住民票のある市区町村に申請します。
相談支援も実施
支援給付と組み合わせて相談支援を実施しています。
お住いの市区町村の相談窓口では、給付のご案内はもちろん悩みや不安などを相談することができます。
深い悲しみや辛く悲しい気持ち、誰にも話せないで孤独を感じている気持ちなど、ひとりで抱え込まず、誰かに聞いてもらうこともとても大切です。
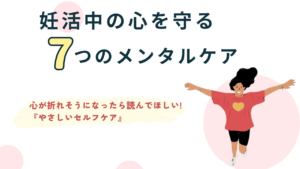
流産の場合の「妊婦のための支援給付」の申請方法
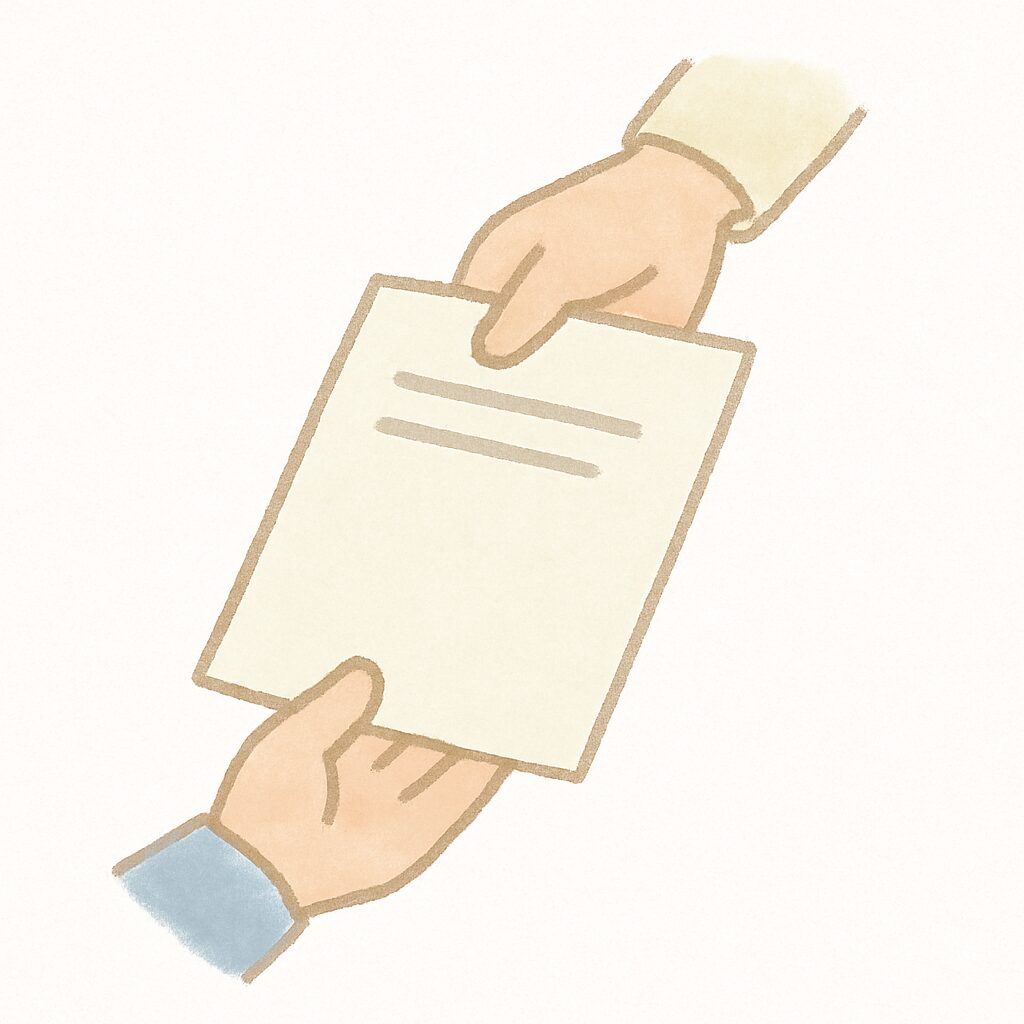
流産の場合の「妊婦のための支援給付」の申請方法は、妊婦給付認定の有無によって異なります。
妊婦給付認定を受けている場合
妊娠届出時に妊婦給付認定を受けている場合は、その認定をもとに妊婦支援給付の申請が行われ、通常は電子申請や窓口申請でスムーズに進みます。
妊婦給付認定がない場合(妊娠届出前に流産した場合など)
妊娠届出をしていない流産の場合は、自治体により申請方法が異なります。
一般的には、以下の書類をそろえた紙申請が求められます。
・妊娠判明時に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書の写し
・必要事項を記入した申請書(紙)
・振込先口座の確認書類
これらを市区町村の窓口または郵送で提出します。
このように、妊婦給付認定の有無で申請手続きの流れや必要書類、申請方法に違いがあるため、居住地の自治体の窓口や公式サイトでの確認が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 中絶(人工妊娠中絶)でも受け取れますか?
→はい、人工妊娠中絶の場合でも、医師が胎児心拍を確認している妊娠であれば支給対象になります。
ただし、胎児心拍が確認される前に中絶処置が行われた場合は対象外です。
Q.2025年4月以前の妊娠・流産も支援給付の対象ですか?
→いいえ、この支援給付の対象となる妊娠は2025年4月1日以降が条件であり、2025年4月以前の妊娠や流産はこの新制度の対象外となります。
Q. 面談を受けていないとダメですか?
→ 面談については自治体により異なりますが、多くの場合、給付申請や妊娠届出時に自治体の保健師や助産師との面談が案内されることがあります。
Q. 申請は代理人でも可能ですか?
→ 代理申請自体は可能ですが、妊婦本人の来所やオンライン面談が後から求められることが多いです。
Q. 振込口座は妊婦本人でないとダメですか?
法律上、妊婦本人名義の口座への振込に限られています。他名義は原則不可です。
※自治体ごとに多少差があるため、必ずお住まいの自治体の公式サイトや窓口で最新情報を確認することを推奨します。
まとめ

流産や中絶は、身体にも心にも大きな負担を伴う経験です。
妊婦のための支援給付金は、そうした経験をした方も「妊婦」として国が認め、支援しようという新しい制度です。
妊娠という事実と妊婦の身体的・精神的・経済的負担に対して支援が必要で、それは流産・死産・人工妊娠中絶の場合も同じです。
支援給付は「妊娠に着目」した支給であるため、妊娠が確定した後の流産・死産も対象。
妊婦の身体的・精神的負担を軽減し、包括的な支援を行うため。
胎児心拍の確認が給付の重要な基準となっている。
経済的支援と共に必要に応じて面談等の支援も想定されている。
「出産していないから関係ない」と思わず、一度お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
知らないままでいるには、もったいない制度です。
心と体のつらさだけでなく、経済的な不安を少しでも軽くするために、この制度をぜひ活用してくださいね!

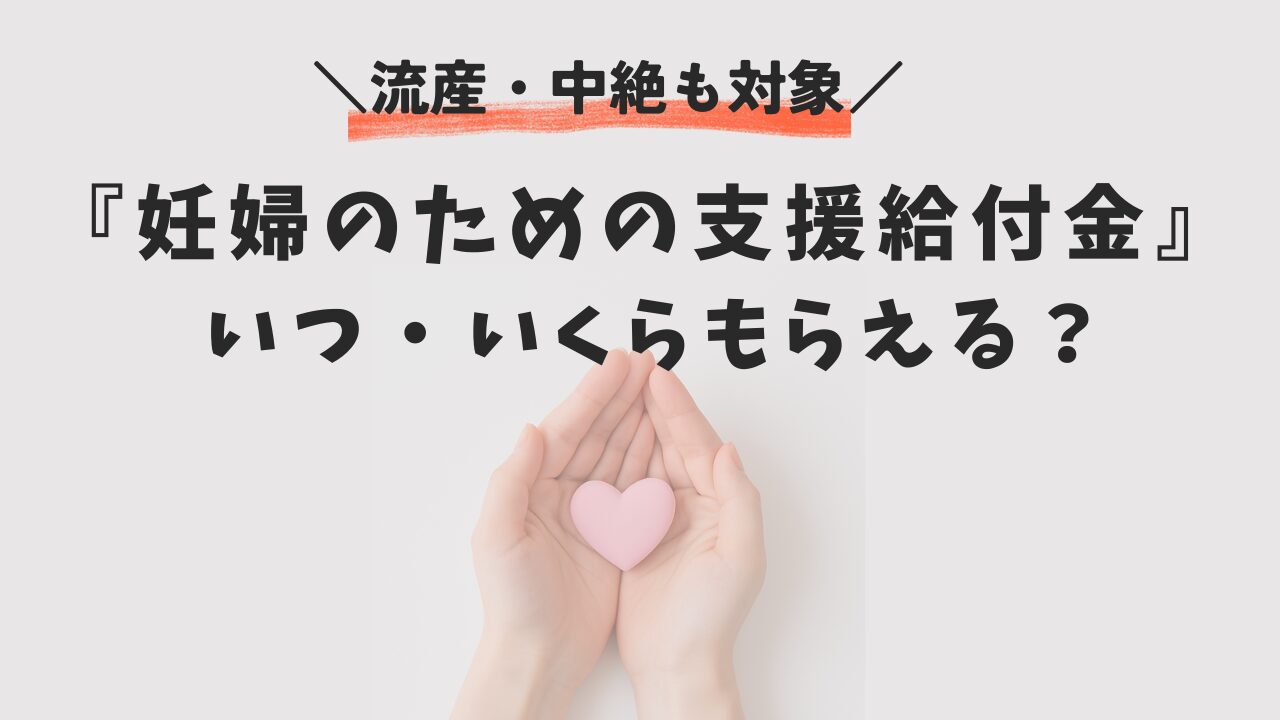
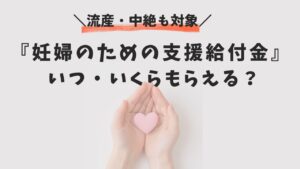
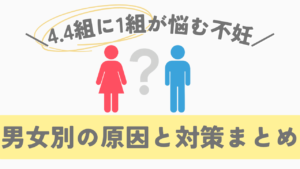
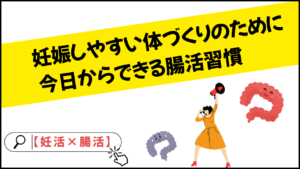

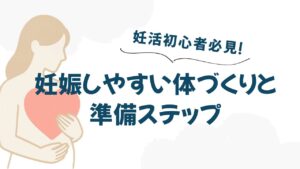
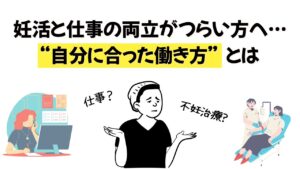

コメント